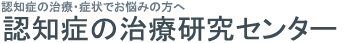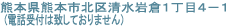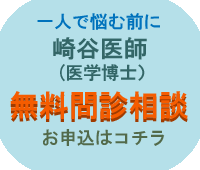FmÇ̤Âa¡ÃAV^CvÌR¤ÂòÉøÊF߸
FmdzÒ̤ÂaǦ̳É¢ÄÍæmçêĢܷB¡ñAVµ¢^CvÌR¤ÂòÅ éZg¨æÑ~^UsÉ¢ÄA}¤ÂÇóðæ·éAcnC}[a³ÒðÎÛÉ_»ÀsQÔñdÓvZ{ÎÆär±iHTA-SADD±jðs¢AøÊÆÀS«ð¢µÜµ½B»ÌÊA¢¸êÌòÜà13T¨æÑ39Tɨ¢Ä¤ÂaÚxXRAÉvZ{ÆÌ·ÍFßçêܹñŵ½iLancet 2011; 378: 403-411jB
RÆ}¤ÂÇó¾©çÆ¢ÁÄA½ËIÉR¤ÂÜð^·éãtªãðâ¿Ü¹ñB±êçÌòÍøʪȢΩèÅÈALQÅ é±Æª èÜ·ÌÅAòàeÍæmFµÜµå¤B
_¶ÌÚ×ÍR`
¨2007N1`09N12ÉpÉ é9ÂÌîÒ¸_ãÃ{ÝÌFmdzҩçQÁÒðåWA2010N10ÜÅÉÊÚðÀ{BAcnC}[aÌÂ\«åiprobableAcnC}[aj¨æÑAcnC}[aÌÂ\« èipossibleAcnC}[aj̳ÒÅA4TÔÈãÌ}¤ÂÇóðæµACornellFmǤÂaÚxiCSDDjXRAª8ÈãÅ éÆ¢¤ðÉYµ½326áðÎÛÒƵ½B
ÎÛÒðAvZ{Qi111áA½ÏNî79ÎjAIðIZgjÄæèÝjQòiSSRIjZg^Qi107áA¯80ÎjAmAhi쮫EÁÙIZgj쮫R¤ÂòiNaSSAj~^Us^Qi108áA¯79Îjɪ¯A13T¨æÑ39TÅÌCSDDXRAðªèµ½BòÊÍT¨«ÉXÉÁAÚW^ÊÍZg150mg/úA~^Us45mg/úÉÝèµ½B
@»ÌÊAeQÌx[XCÆärµ½13TÅÌCSDDXRAÍAvZ{Q−5.6iWη4.7jAZg^Q−3.9i¯5.1jA~^Us^Q−5.0i¯4.9jÆA·×ÄÌQɨ¢ÄẵAÅàvZ{QÌẪÅàå«©Á½B39TÅÍAvZ{Q−4.8i¯5.5jAZg^Q−4.0i¯5.2jA~^Us^Q−5.0i¯6.1jÅ Á½BȨA39TÜÅ̯±E¦ÍAZg^Q35i37ájA~^Us^Q29i31ájAvZ{Q24i27ájÅ Á½B
@ÉAÔâ¡Ã{ÝÅâ³µ½¬ü`ñAfðp¢ÄCSDDXRAð]¿µ½B»ÌÊAvZ{QÆä×½¯XRA̽ϷÍA13TÅÍZg^QÅ1.17iWë·0.72C95CI −0.23`2.58CP=0.10jA~^Us^QÅ0.01i»ê¼ê0.70C−1.37`1.38C0.99jA39TÅÍÉ0.37i»ê¼ê0.76C−1.12`1.87C0.62jA−0.66i»ê¼ê0.74C−2.12`0.79C0.37jÆALÓ·ÍFßçêÈ©Á½B
@¯lÉA~^Us^Q̯XRAÆä×½Zg^Q̽ϷÍA13TÅ1.16i»ê¼ê0.72C−0.25`2.57C0.11jA39TÅ1.04i»ê¼ê0.76C−0.45`2.53C0.17jÆAÀòQÔɨ¯éLÓ·àmF³êÈ©Á½B
@ܽAÀS«É¢Äࢵ½Æ±ëA39TÜÅÉLQìpªFßçê½ÌÍAvZ{QÅ29ái26jAZg^QÅ46ái43jA~^Us^QÅ44ái41jÅ Á½BåÈÇóÍAZgÅÍ«SA~^UsÅÍ°CâÁÃÅ Á½B
¡{îñELÌì ÍSÄèJ¤ÉA®µÜ·BÂÈ¡»yÑ]ÚÈÇ·é±ÆðÅֶܷB³f¡»A]ÚyÑzM͹Q Aì @̱¥ÌÎÛÆÈèÜ·B