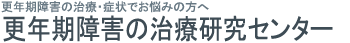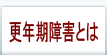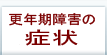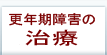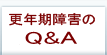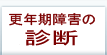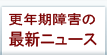q{Eo«ÖÌGXgQPÆÃ@A]²AìðÇðÇXNÍîüI¹ãÉÁ¸
Âoã«ðÎÛÉzâ[Ã@iHRTjÌøÊðص½ÄÌåKÍ_»är±iRCTjWomen's Health InitiativeiWHIjB»Ì¤¿AN«ðÎÛƵ½±ÍAGXgQÆvQXe¹pQÅZ«ûªñÌXNÌ㸪Fßçê½½ßÉ2002NÉ~³êܵ½B
êûAq{Eo«ð^GXgQiCEEjÆvZ{Éèt¯½±ÍA½Ï7.1NÇÕÌãA]²ÈÇÌXNã¸ðó¯A\èæè1N¢2004N2É~³êܵ½B
Ätbhnb`\ªñ¤Z^[ÉæÁÄA^GXgQPÆÃ@±QÁÒÌNXNðñ11NÔÇÕ³êܵ½BîüI¹ãA]²âìðÇðÇiVTEjÌXNã¸ÍÁ¸µASÇÕúÔðʵĥ®¬¾³iCHDjASÈÇÌXNã¸àÈ©Á½êûÅANîwÉæèXN·ª é±Æª_¶ñ³êܵ½iJAMAi2011; 305: 1305-1314j
ÄÌåKÍ_»är±WHI±Ì^GXgQPÆÃ@±ÅÍA1993`98NÉÄ40{ÝÅo^³ê½50`79ÎÌq{Eo«1739áªCEE 0.625mg/úÆvZ{É_Éèt¯çêܵ½B^GXgQQɨ¯éîüÌCxgÌnU[häÍA¥®¬¾³É¢ÄÍ0.95i95CI 0.78`1.15jŵ½ªA]²1.36i¯1.08`1.71jA[ìðÇiDVTj1.47i¯1.06`2.05jAxðÇðÇ1.37i¯0.90`2.07jÅ㸵AZ«ûªñ0.79i¯0.61`1.02jAåÚßÊÜ0.67i¯0.46`0.96jÅẵĢĢܵ½B
³çɯӪ¾çê½7,645á̶¶Òð2009NÜÅÇյܵ½B^GXgQgpúÔÌlÍ5.9NA½ÏÇÕúÔÍ10.7NÅAîüI¹ãi2004N3`09N8jÌGXgQgpÍ^GXgQQÅNÔ3.6`4.7AvZ{QÅ2.7`3.0ŵ½B
1]¿ÚÍ¥®¬¾³ÆZ«ûªñƵA»Ì¼É]²AxðÇðÇAå°ªñAåÚßÊÜASðÜÞ«¾³O[oCfbNXð²×ܵ½B
ªÍÌÊA¥®¬¾³ÆûªñÌîüãXNiN¦jÍîüÆÙÚ¯lÅA^GXgQQðvZ{QÆär·éÆA¥®¬¾³0.64 vs. 0.67%inU[hä0.97A95%CI 0.75`1.25jAûªñ0.26% vs. 0.34%i¯0.75A0.51`1.09jŵ½BȨASÇÕúÔÅ©éÆAûªñÍ0.27% vs. 0.35%ÆÈèA^GXgQQÅLÓɸµÄ¢Üµ½i¯0.77A0.62`0.95jB
]²É¢ÄÍ0.36% vs. 0.41i¯0.89A0.64`1.24jÅAîüÉ©çê½]²ÌÁÍàÍâFßçêܹñŵ½B¯lÉ[ìðÇâxðÇðÇÌÁXüàÁ¸µA[ìðÇÉ¢ÄÍ0.17% vs. 0.27%i¯0.63A0.41`0.98jÆ^GXgQQÅXNªá©Á½B
êûA^GXgQQɨ¯éåÚßÊÜXNáºÍîüãÉÁ¸B0.36% vs. 0.28%i¯1.27A0.88`1.82jÆA^GXgQQÅí¸©ÉXNª©Á½B
îüãÌSÍ1.47% vs. 1.48%i¯1.00A0.84`1.18jŵ½B
³çÉASÇÕúÔÖÌ^GXgQÌe¿ð50`59ÎA60`60ÎA70`79ÎÌNîwÊÉص½Æ±ëA50`59ÎÅÍ¥®¬¾³ASSØ[Ǫ¸µA70`79ÎÅÍ°¼°ªñA«¾³O[oCfbNXªÁB
Nîªá¢O[vÅAEgJªÇDÅ Á½ÚÌðÝìpÌPlÍA¥®¬¾³0.05ASSØ[Ç0.007Aå°ªñ0.04AS0.04A«¾³O[oCfbNX0.009ÆANîwÉæèXNªÏ®·é±Æª¦´³êܵ½B
Èã̱ƩçAXNúáQÉηézâ[Ã@±üÌÛÍA³ÒÌNîâq{EopÌL³ÉæÁÄÙÈÁ½à¾ªKvƳêÜ·B¡ñ̤ÎÛÌ^GXgQÌgpúÔÍ5.9NÅ èA·úgpÌXNxltBbgÉ¢ÄÍs¾ÆµÄ¢Ü·B
¡{îñELÌì ÍSÄèJ¤ÉA®µÜ·BÂÈ¡»yÑ]ÚÈÇ·é±ÆðÅֶܷB³f¡»A]ÚyÑzM͹Q Aì @̱¥ÌÎÛÆÈèÜ·B